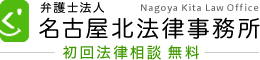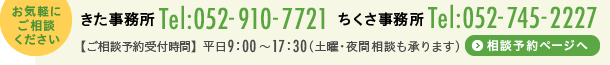DV被害防止の現状
2025年9月16日
近年、配偶者やパートナーからの暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)に関する相談が急増しています。配偶者暴力相談支援センターの集計では、2002年度に3万5943件だった相談件数が、2022年には12万2211件へと3倍以上となっています。「DV(ドメスティック・バイオレンス)」は身体的暴力だけでなく、精神的暴力や経済的圧迫、性的強要も含まれます。「モラルハラスメント(モラハラ)」は、主に言葉や態度による精神的な攻撃で、被害者の自己肯定感を奪い、社会的に孤立させるものです。
DV被害者の保護の体制
現在、配偶者暴力防止法(DV防止法)では、DV被害者を守るために様々な制度があります。都道府県が設置する女性相談支援センター等では、相談支援又は相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時における安全の確保及び一時保護、自立支援等の情報提供を行っています。#8008の電話番号で近くの相談機関につながります。警察においても、女性相談支援センター等と連携して必要な相談につなげています。警察が加害者に口頭で注意をする、被害届を受理して刑事事件として捜査することもあります。
保護命令について
DV防止法では、被害者を守るために裁判所が決定を出し、加害者に対して、被害者、子供、親族等への接近や連絡を禁止する「保護命令制度」があります。2022年の保護命令事件(1453件)のうち、保護命令が発令された件数は1111件であり、7割以上で認められている実態があります。
現行制度では、同棲中の恋人や元交際相手など、婚姻関係にない相手との間の暴力には保護命令が出せないという制約があるため、現在「親密な関係にあった者」全般を対象に含める方向で調整が進められています。
おわりに
このように、DV被害を防止するために様々な制度があります。ただ、相談件数の増加に人員体制が追いついていない、予算不足のために困難な相談に対応できる専門的な人材の養成が出来ていない等の問題があります。DV被害に対して社会が関心を持ち続けることが必要です。
弁護士 白川秀之(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)