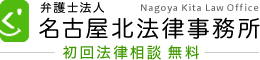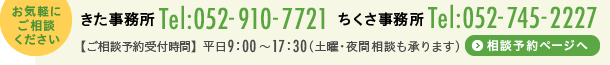中小企業メールマガジン No.13
2010年11月10日
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
弁護士法人名古屋北法律事務所 ホウネット
中小企業メールマガジン No.13(10月13日発行)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
最近、出かけるときには、半袖か長袖のどちらを着るかを考えます。半袖を着る
と肌寒く、長袖では暑く感じます。そのため、長袖を着て、暑くなったら袖を折り
、肌寒くなったら折った袖を伸ばして温度調節をしています。こんな風に季節の
変わり目を肌で感じている今日この頃です。あともう少しすると、長袖の上に何
を着ようかと考える季節になりますね。
∞∞∞I N D E X∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
○コラム
◆◇「連載 取締役の責任(3)
名目的な取締役・監査役の責任と責任限定契約」◇◆
弁護士 長谷川一裕
◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆
『労働者の健康と安全(13)−過労死について−』
弁護士 加藤 悠史
○ホームページ更新情報
○編集後記
■□コラム━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇「連載 取締役の責任(3)
名目的な取締役・監査役の責任と責任限定契約」◇◆
弁護士 長谷川一裕
中小企業、特に従業員も少ない小規模の企業では、取締役の員数を揃える
ため親族等に名前を貸して貰い取締役・監査役に登記するということが良くあり
ます。典型的には、社長の妻が監査役、兄弟や両親が取締役といったパターン
です。そうした会社では、会社法に基づく取締役会が全く開催されなかったりしま
す(株主総会すら開かれない会社も少なくありませんが)。
問題が起きない場合には良いのですが、幹部従業員に取締役になってもらうケ
ースも少なくありません。しかし名目的な会社役員と言えども、会社法上の責任
は免れず、任務懈怠の場合には損害賠償責任を負うことを銘記する必要があり
ます。
取締役の損害賠償責任は、(1)会社、(2)株主、債権者等の第三者に対する
責任、(3)その他の責任に分類することができますが、例えば、代表取締役が経
営権を濫用し、会社の資金を投機時取引で浪費した場合を想定しますと、代表
取締役が投機取引に手を出していること、会社資金が投機資金に流用されてい
ることは、帳簿等の会計資料を閲覧したり、取締役会で業務執行状況を審議して
いれば、当然把握できる事柄であり、その結果、会社が損失を受けた場合には、
役員としての損害賠償責任を負います。
それでは、「名前だけでも取締役になってほしい」と言われも断れない場合、
責任を限定し、リスクを回避することはできないのでしょうか。
会社法第425条は、取締役の責任について4年間の受領報酬額、監査役
について2年間の報酬額を責任額の上限とすることを株主総会で決議すれば、
その範囲内に賠償責任を限定することができます。
但し、「故意または重大な過失がない場合」に限り、ということです。先の例では
、代表取締役が会社資金で投機取引をやっていることを知っていた場合等には、
責任限定の株主総会決議は役に立ちません。くれぐれも気をつけてくださいね。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
◆◇「中小企業経営に役立つワンポイント豆知識」◇◆
『労働者の健康と安全(12)−過労死について−』
弁護士 加藤 悠史
労災について、労災保険給付の内容から通勤災害及び業務災害の注意点に
ついて連載してきましたが、今回は過労死について触れたいと思います。
いまでは有名な話になりましたが、過労死というのは世界的にもまれに見ること
で、欧米では元々「work oneself to death」と翻訳されていたものが、「Karoshi」と
して通用するようになっています。
社会的にも認知されてきているので、イメージは分かりやすいと思いますが、
具体的には、長時間残業や休日なしの勤務が精神的・肉体的な負担になり、そ
の結果、労働者がくも膜下出血、脳梗塞等の脳血管疾患や、心筋梗塞や狭心症
等の虚血性疾患等により死亡することを言います。
厚生労働省のマニュアルでは、「過労死とは過度な労働負担が誘因となって、
高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化し,脳血管疾患や虚血性心疾患、急
性心不全などを発症し、永久的労働不能または死に至った状態をいう」とされて
います。通常の労災と同じですが、死亡が業務によるものかどうかが問題になる
のですね。
過労死の場合には、労働基準監督署は次のような死亡前の労働時間の基準
に従って疲労の蓄積によるものか否かを判断します。
(1)発症前1ヶ月ないし6ヵ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね45時間を超え
て時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる。
(2)発症前1ヶ月間におおむね100時間、又は、発症前2ヶ月ないし6ヵ月間にわ
たって1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合には、
業務と発症との関連性が強い。
労働基準監督署は、この基準を重視しますが、裁判例では、労働時間が上
記基準に達しない場合でも業務の加重性や本人の要因を考慮して業務による
死亡であると認められるケースもあります。
このメルマガでも話をしてきましたが、使用者には、雇用契約に付随する義務と
して、従業員がその従事する業務によって健康を害しないよう労働時間や労働条
件等の環境を整備し、労働者の安全を配慮すべき義務、つまり安全配慮義務を
負担しています。長時間労働が原因となって死亡した過労死の場合にも、労災
だけではなく企業の責任が問題となりえます。
使用者としては労働者が健康に働けるように、(1)時間外労働の削減(2)年次
有給休暇の取得促進(3)健康診断の実施(4)産業医等による助言指導などを
心がける必要があるわけです。
皆さんの会社でも一度チェックしてみて下さい。
■□ホームページ更新情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎夏の青春18キップ 「只見線までの700キロの道のり」
ホウネット経営塾 塾長・参与 立木勝義
2010年9月2日(木)名古屋駅午後11時20分発の東京行き臨時夜行列車―
快速「ムーンナイトながら」で東日本方面の一泊2日のローカル線の旅に出発し
ました。
http://www.kita-houritsu.com/?p=2462
◎HP「知って得する法律情報」
HPにある「知って得する法律情報」では、ホウネット経営塾の講義レポートや
最新の法律情報が多くあります。是非ご覧ください。
http://www.kita-houritsu.com/lawnews/
■□編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━
尖閣諸島での中国漁船船長の公務執行妨害事件、人権活動家のノーベル受
賞とこれに対する中国国内での言論抑制問題等が中小企業家の間でも話題を
呼んでいます。今や日本の最大の貿易相手国であり、重要な隣国です。もちろ
ん友好関係を大切にしなければなりませんし、対日感情が思わしくない根本原因
の一つに日本が侵略戦争の反省を十分してこなかったことがあることも忘れては
なりません。
しかし、前者の事件について言えば、尖閣諸島が日本に帰属することは明らか
であり、領土主権を脅かすような問題については原則的な対処が必要です。また
、後者の中国における人権状況に関する問題については、中国の国内問題とは
いえ、アジアの国民として大きな関心を抱き続けるべきテーマです。戦後の国連
憲章の精神は、平和のためには、基本的人権が保障されなければならないとい
うものです。国連が人権問題に取り組む根本的な立脚点はそこにあります。日
本軍国主義の歴史を見るまでもなく、言論が抑圧され、基本的人権が保障され
ない社会では、国家が拝外主義を鼓吹し、戦争を準備することを許すことになる
からです。
中国は、時々、「未だ途上国ですから」という「抗弁」を使いますが、国連安保理
の常任理事国なのですから、少なくとも領土保全とか人権尊重といった国連憲
章の根本的定理については、もう少しこれを尊重し、周辺諸国からも信頼される
大国として成長していってほしいと願わずにはいられません
(弁護士 長谷川一裕)。
当メールマガジンにご感想や御意見がございましたら、下記アドレスにて返信し
てください。
↓↓↓↓↓ご感想や御意見はこちらから↓↓↓↓↓
hounet-sme@kita-houritsu.com
↓↓↓↓↓ブログのバックナンバーをご覧できます↓↓↓↓↓
https://g104.secure.ne.jp/~g104135/melmag/
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
【中小企業メールマガジン】
中小企業メールマガジン No.13(10月13日発行)
発 行 日:月2回・月曜日発行(休刊:祝日、年末年始など)
創刊日:2010年4月5日
↓↓↓↓↓本メールマガジンの登録はこちらから↓↓↓↓↓
hounet-sme@kita-houritsu.com
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇