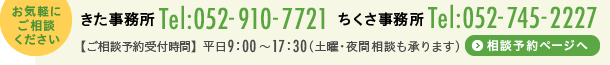西野喜一元裁判官「裁判員制度の正体」(講談社現代新書)を読む1 豆電球No.48
2008年3月11日
西野喜一元裁判官「裁判員制度の正体」(講談社現代新書)を読む1
「恐怖の悪法を徹底解剖」「日本の司法を滅ぼす、問題山積の新制度」等というタイトルに惹かれてだいぶ前に買っておいた本で、なかなか読む機会に 恵まれなかったが、新潟県弁護士会が裁判員制度の導入の延期を決議したというニュースに接し、きっと西野さんのこの本が種本であろうと考え、読むことにし た(西野氏は、新潟大学教授である)。
裁判員を免れる方法を伝授することをキャッチにしており、ふざけた話だなと思っていたが、まっとうな中身もある。日本の刑事裁判のことを真摯に考えてい る姿勢は評価できる。 陪審制や裁判員制度の問題点を具体的に指摘しており、裁判員制度の運用の上で、参考にすべき点もある。
私は、西野氏は知らないが、名古屋に在任していた時もあり、時々、駄洒落を飛ばすおもしろい裁判官であったと聞いたことがある。本書を読んで、きっと、その良心に従い、誠実に刑事裁判に取り組んでおられた裁判官であった違いない、と思った。
序言で、西野氏は、次のように言っているが、ここに西野氏の主張のエッセンス、この本を著した動機が端的に示されている。
「裁判の対象となっているのは、犯罪という重大で、そして実際には極めて稀な現象です。普通の常識人なら誰でも体験していて、誰でもこれに基づいて健全 な判断ができるというものではない。これに対して、裁判官は、専門的な訓練を受けているだけでなく、職務上膨大な数の事件、犯罪を見て、これを証拠に基づ いて判断し、その判断の過程を合理的に文章で表現するという仕事を何十年もやっています」「このような彼らの仕事熱心さとモチベーションの高さはを生かし た訴訟制度を構成するのが一番合理的で賢い政策です」「しかるに、裁判員制度は、裁判官に対して、おまえたちの判断だけでは信用できない(中略)という メッセージを送っている。ですから、裁判官の士気が大きく落ちることも、裁判の内容が粗雑になってしまうことも確実と思われます」
どうやら西野氏は、裁判員制度が、プロとしての刑事裁判官に不信任を突きつけられたものと感じたようである。いかに日本の職業的裁判官が誠実で有能であ るかを力説し、素人の参加への強い拒絶感を示しているのである。西野氏は、そうではないと思うが、専門家が独占していた分野に一般市民が参加しようと言う のであるから、当の専門家の一部に、自分の沽券に関わるとか、そんじょそこらの素人に俺達の仕事ができる筈がない!と力む人が仮にいたとしても、それはそ れとして自然というものである。
西野氏のプロとしての意気は大いに買いたい、と言いたいところだが、いささか職業裁判官の実態を美化し過ぎているところがある。また、裁判員制度の導入の趣旨を正解してない点があると思う。以下、率直な感想を記してみたい。
まず、第1に、裁判員制度は、決して職業裁判官の専門性を無視した制度ではない。司法の国民参加については、様々な論議があり、陪審制の導入も強く主張 されたが、裁判員制度は、裁判官の専門性を生かすととともに国民の良識を反映させ、両者の協働によって刑事裁判を行うというものである。
西野氏は、職業裁判官の優秀性、誠実性を強調されるが、いささかエリート意識の匂いがしないではない。対照的に、市民代表としての裁判員については、「裁判員は小学校卒業しか要件とされていない」という言葉が繰り返し出てくる。
その昔(と言っても最近退官したばかりだが)、名古屋には、「起訴状一本主義」あるいは「新聞記事一本主義」と弁護士仲間で揶揄されていた刑事裁判官が いた。起訴状一本主義というのは、裁判官が予断を持たないで公判に臨むため、起訴状には添付資料をつけてはならないというものであるが、その裁判官は、起 訴されただけで有罪と決めつけてしまうという、あるいは新聞記事だけで有罪と決めているのではないかという皮肉である。偏見を持った職業裁判官ほど、たち の悪い存在はない。西野氏も似たようなことを言っているが、裁判官は、自分の出した結論を合理化するための理屈を組立て、表現することに長けているからで ある。痴漢冤罪事件をテーマにした映画「それでも僕はやっていない」を見た人なら、これは判ってもらえると思う。
西野氏は、毎日のように証拠に基づき事実を認定し裁いてるから、真実を見抜けると言う。しかし、毎日、同じ仕事を繰り返しているからこそ生まれる弱点、 陥穽もある、と考えたことはないのだろうか。ルーティーンになってしまうと、どうしても、気の緩み、惰性や慢心が生じたり、思いこみが生じたり、自分の狭 い経験から物事を判断する経験主義に陥ったりしがちなのが、人間である。
その危険性を裁判官だけが免れていると考えるのは、楽観的に過ぎるというべきだ。
法廷で「二度としません」と反省の弁を述べながら、刑務所と社会の往復を繰り返す常習累犯窃盗や寸借詐欺の被告人たち。鞄の中に覚醒剤を所持していると ころを現行犯逮捕され、「自分は鞄の中にあることは知らなかった」「誰かが入れたに違いない」という覚醒剤取締法違反の否認事件は、10年以上のキャリア を持つ弁護士なら誰でも一度や二度は遭遇する(もちろん、これらの弁解をする被告人の中には本当に冤罪の場合もあるだろうが、全てが冤罪でないことも当然 である)。こういう被告人を毎日、裁いていると、どうしても、被告人に予断を抱いたり、偏見が生じたりすることは避けがたいところがあるのではないだろう か。そうしたなかで、無罪の推定という原則を堅持し、本当の冤罪事件を探り当てるということは、そんなに容易なことではない。
裁判員制度は、裁判官の専門性を尊重、評価しつつ、その弱点を補強し、市民との協働により、よりよい刑事裁判を実現し、ひいては司法を市民に身近なものとし、司法の国民的基盤を確立することをめざすものである。
裁判員は、はじめて経験する刑事裁判に緊張して参加する。裁判官は、審理が始まる前に、必ず、法廷にあらわれた証拠のみから有罪か無罪かを判断しなけれ ばならないこと、疑わしいだけでは有罪とはできず、合理的な疑いを容れる余地がない程度に検察官が立証した場合に限って有罪にすることができることを懇切 に説明しなければならない、とされている。その教示は、裁判官自身の心に生じた緩みを正し、改めて無罪推定の原則を心に刻みつける契機ともなりうるだろ う。
日本の職業裁判官というものは、大学を優秀な成績で卒業し、まっしぐらに司法試験の受験勉強に打ち込み、司法研修所を卒業して判事補になるところから出 発する人が多い。私たちの時代は、東大の法学部生で司法試験に進んだ学生の多くが人権派弁護士を志していたが、最近は、東大を出た修習生は、裁判官や検事 に任官するか、大企業の仕事が多い渉外事務所に就職する例が多いと聞く。心配なことだ。
法律の専門家だからと言って、必ずしも、人間や社会の実情に明るいとは限らない。エリート街道を歩き続け、社会生活の幅も狭い裁判官に、社会の底辺を這 いずり回るように生きている人々の生活や感情が理解できるだろうか。例えば、老々介護で苦しんた挙げ句、殺人や嘱託殺人に走る事件が後を絶たないが、介護 がどんなにしんどいものなのか、どんなに被告人が追い詰められた状態にあったのか、理解できるだろうか。
裁判員には、専門的知識はないかもしれないが、人生経験では遙かに先輩である方や個性的な面々がいるであろう。是非、こうした人々の意見にも謙虚に耳を傾けてもらいたいと思う。
西野氏は、裁判員制度導入は、裁判官は信用できないと言われてるいるようなものだとか、士気が下がると言われる。しかし、そうむくれないで欲しいのであ る。むしろ、裁判員制度のもとでこそ、経験豊かな職業裁判官の腕が、力量が試される。事実認定と量刑のプロというなら、その自負があるなら、自らが形成し た心証について、証拠と論理に基づいて裁判員を説得できる筈であり、それはやりがいのある仕事ではないのか(裁判員制度の評議では、裁判官は黒子に徹すべ きで、余り発言すべきではないという意見もあるというが、私はそうは思わない。謙虚でなければならず、裁判員の率直な意見交換が行われるような雰囲気作り の重要性は言うまでもないが、それは裁判員に迎合することではない。この点については、別の機会に触れたいと思う)。
行政について「説明責任」ということが良く言われるようになった。行政の民主化にとって説明責任は極めて重要なキーワードになっているが、裁判員制度は、いわば、司法の場で、裁判官に、市民代表に対し説明責任を果たすことを求める意味もあるのである。
裁判員になった人は、自ら裁判官席に座り、犯罪被害をこの目で見たり、被害者の心情を聞いたり、被告人の真剣な弁解を聞いたりする中で、裁判や司法をよ り身近に考えるであろう。刑事裁判とは何か、被疑者・被告人の防御権の重要性を知る契機になるかもしれない。さらには、犯罪がなぜ生まれるのか、民主主義 とは何か、自己統治とは何かを考える機会になる可能性もあるだろう。それは、市民に縁遠い司法の国民的な基盤を強めることにつながる可能性もある。裁判員 制度導入は、こうした重要な意義があるのであり、その要の要諦として重要な仕事をするのが刑事裁判官である。
西野氏には、裁判官室の蛸壺のなかだけで物事を考えるのではなく、日本の統治システムの変革という、もっと大きな視野に立って裁判員制度というものを見 直して欲しいと思う。 また、刑事裁判官の大先輩として、こうした重要な意義を持つ裁判員制度に携わることになるであろう刑事裁判官を叱咤激励し、その 「士気を高める」ような発言を期待したいものである。